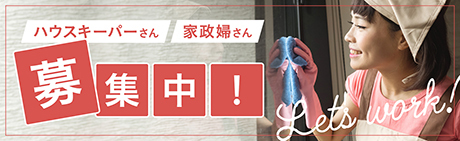大掃除といえば年末に行うのが恒例ですが、忙しい年の瀬に家中をきれいにするのは大変です。そこで、1年のはじまりの今の時期に1年かけて家の掃除を進めるスケジュールを作成してみるのはいかがでしょうか?近年のコロナ禍では在宅時間の増加に伴い、日々の掃除時間が増えたことから「年末の大掃除は不要」というトレンドも生まれています。

家事代行マッチングサービス「タスカジ」なら、1時間1,500円からリビングやキッチン、普段のお掃除が行き届かないお風呂やトイレなど水回りまで、家事のプロに依頼することができます。依頼の予約はWEBやアプリから手軽にできるため、ぜひお試しください。
家事代行を利用してみる
年末の恒例行事「大掃除」の由来とは?
年末の慌ただしい時期の大掃除は、面倒だと感じる方も多いでしょう。大掃除をしなくてももちろん年は越せますが、なんとなくきれいにしておかないと正月を気持ちよく迎えられないと感じる方も少なくありません。そもそもなぜ大掃除をしなければならないのでしょうか。まずは大掃除の由来などを探ってみましょう。
大掃除の由来
年末に神社仏閣で行われる「すす払い」が起源とされています。神社仏閣では、現在も「すす払い」が行われていますが、一般家庭ではこの「すす払い」が現在の大掃除へと変わっていったようです。また、大掃除はお正月の神様を迎えるために行う準備とも言われています。大掃除には「家と心を清め、お正月の神様をお迎えする」という意味があるのです。
年末に大掃除をするのは日本だけ?
海外では、年末に大掃除する風習はないようです。ヨーロッパでは「スプリング・クリーニング」といって春に大掃除をし、中国では春節に大掃除をする文化があります。アメリカでは春に掃除や家の補修をすることが多いようです。
「大掃除」をしないという選択肢も
年末に大掃除をするのは大変
寒くなってくると、どんどん水を使うシーンが億劫になっていきます。真冬に窓を開け放して、水を使う掃除をするのは大変です。特に、油汚れは気温の高い季節に掃除するほうが効率もよく、少しでも暖かい時期を狙って済ませたほうが得策だと言えます。
大掃除をしないという選択
ある家事代行業者が行なったアンケートでは、年末に大掃除をしない人は全体の4割ほどで、そのうちの4割が日頃から掃除をしていることを理由に大掃除をしていなかったという結果が得られました。1年かけて少しずつ家中の掃除を進めておけば、年末に大掃除をする必要はないのです。
年間の掃除スケジュールを作成してみよう
年間の掃除スケジュールを立ててこなしていくと、年末にまとめて大掃除する必要がなくなります。今回は掃除スケジュールの作成方法を2つご紹介します。
掃除頻度ごとにチェックリストを作成する方法
<掃除をリストアップする>
普段している掃除に加えて、大掃除のときにしている掃除もすべて書き出してみましょう。掃除すべき場所がわかると、スケジュールが立てやすくなります。
<頻度別に掃除チェックリストを作成する>
週1・隔週・月1・シーズンごと・年1回というように、掃除頻度ごとに分けてチェックリストを作成しましょう。チェックリストは手書きでもExcelやアプリなどを利用してもよいです。目につく場所に貼っておくと、常に意識できるので掃除への意欲も高まり、忘れ防止にもつながります。
<チェックリストを張り出して家族で分担しよう>
掃除を見える化し、家族みんなで分担できるようにしましょう。何をしたらいいのか見てわかることで、子どもも理解しやすくなり、積極的に掃除してくれるようになるはずです。将来のことを考えて、子どもに掃除の習慣を身に付けてもらうチャンスでもあります。また、旦那さんのほうが適している作業もありますので、それぞれが無理のない役割分担で掃除が進められます。
月ごとに掃除場所を決める方法
<場所ごとに計画する>
1か月で1つの場所を掃除するイメージで計画すると、わかりやすくておすすめです。掃除の手間がかかる、キッチンなどのような場所は数か月に分け、汚れが少ない部屋はまとめて掃除するなど、無理のない計画を立ててみましょう。
<季節に合わせて計画する>
水を使う場所や油汚れのある場所は気温の高い季節に掃除しましょう。そうすれば寒い思いをしなくて済み、油汚れも浮きやすいため、掃除もはかどります。気温が低い季節は、クローゼットや収納スペースなど、あまり水を使わない場所を掃除するのがおすすめです。
<無理のないスケジュールにする>
スケジュール通りに進めていくためにも、無理のない計画を立てましょう。また予備月として、掃除の計画を入れない月を設けておくと、スケジュール通りに掃除ができなくても予備月で取り戻せるため、気持ちに余裕が生まれます。
年末の大掃除を家事代行に依頼するなら「タスカジ」へ

家事代行で家事を定期的にアウトソーシングするなら、品質はもとより、できるだけ料金を抑えたいものです。リーズナブルな料金で依頼したい方へおすすめしたいのが、株式会社タスカジが運営する家事代行マッチングサービス「タスカジ」です。
家事代行サービスを提供する「タスカジさん(ハウスキーパー)」と家事代行を依頼したい個人とをマッチングさせるシステムになっています。手軽にリーズナブルな料金で利用できることから、近年大人気の家事代行サービスです。
以下のポイントを魅力に感じる方に、特におすすめのサービスといえます。
- 1時間あたり1,500円から利用できる
- キャンペーンコードや定期依頼で利用するとさらに安くなる
- 家事代行の依頼をネットで完結できる
まとめ
年末が近くなってから一気にやろうとすると、慌ただしくなってしまい大変です。疲れ切るほどの大掃除をこなしたことで、お正月に体を壊してしまっては元も子もないでしょう。年間で掃除スケジュールを立てて、コツコツと掃除したほうが得策です。また、タスカジを利用することで、立てた掃除スケジュールを無理なく進める方法もあります。ぜひ日々の掃除にタスカジのサービスをお役立てください。
株式会社タスカジの代表取締役。国内大手ITベンダーに入社。その後MBA(経営学修士)を取得。2013年に共働きの家庭における新しいライフスタイルを実現するため、起業。2014年に家事代行マッチングサービス「タスカジ」を開始し、2017年に日経BP社 日経DUAL「家事代行サービス企業ランキング」1位、「日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー2018働き方改革サポート賞」を獲得。
多くの人が自分らしく生きる時間を増やせる社会を実現するため、一般家庭でも気軽に質の高い家事代行を利用できる仕組みを作るという想いで「タスカジ」を立ち上げた。